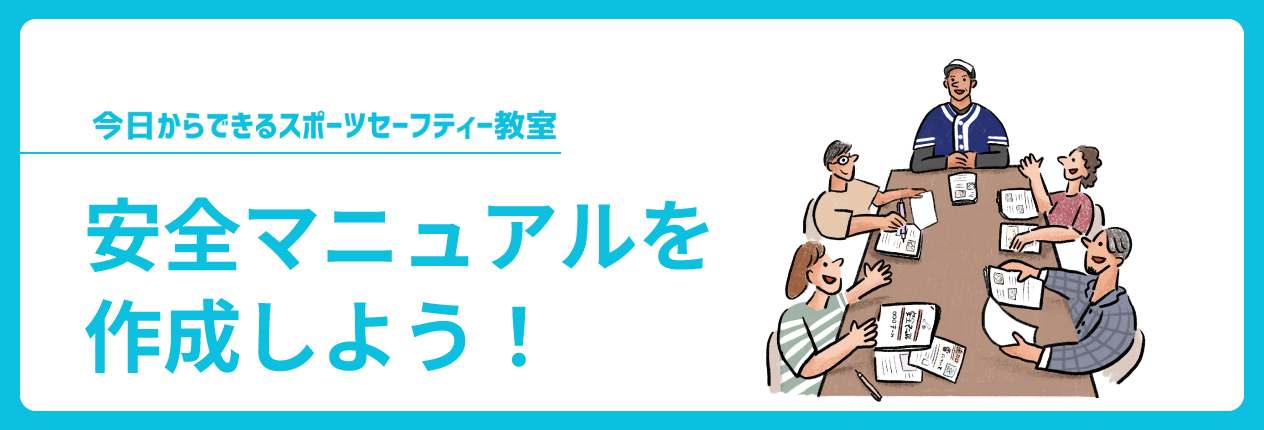
スポーツを安全に行うために、競技団体などが発行している安全に関するガイドラインなどに沿って、ご自身のスポーツ現場での安全マニュアルを作成してみましょう。今回は指導者や保護者の方にとっても分かりやすい、安全マニュアル作成の重要性について解説します。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、起こり得る危険を事前に予測し、回避することをいいます。起きた事故が最小限に抑えられるような救護対応も「回避」につながります。
この安全配慮義務は、全てのスポーツ現場やイベント運営で求められる法的責任です。安全配慮義務を果たすためには、起こり得る危険を想定し、回避するための対策を講じる必要があります。
スポーツが安全に行われる環境は、事前の体制づくりと事故後の対応の両方が整って初めて実現します。
この事前の体制づくりと事故後の対応を書面化したものが安全マニュアルです。
安全マニュアルとEAPの違い
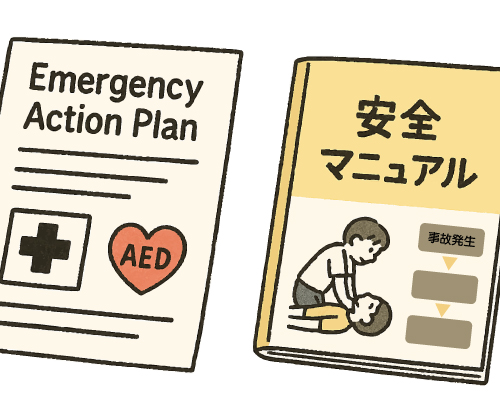
安全マニュアルとEAP(Emergency Action Plan、緊急時対応計画)の2つは同じものとして扱われる場合がありますが、この2つには大きな違いがあります。
EAPは、あくまでも緊急事態が起こったときに適切かつ迅速に救急対応を実施するために事前に作成される1枚の書類です。
掲載記事: EAPを作成し、救護体制の準備を万全に!
一方、安全マニュアルには、心肺停止や頭や首のケガ、熱中症、落雷事故などの緊急事態1つずつにおける救急対応の手順が記載されます。
緊急事態の救急対応だけでなく、事故やケガを未然に防ぐために事前にリスクを抽出し、どのようにそれらのリスク軽減を講じるかなどの対策も含まれます。
当会の学童保育における安全計画策定支援のページで紹介している「安全計画策定のための各種マニュアルサンプル」の事故防止・事故対応のサンプルマニュアルを参考に作成するのも良いでしょう。
状況や実態に合わせた安全管理体制の構築
安全配慮義務を果たすためには、各スポーツ現場の状況や実態に合わせて安全管理体制を構築し、安全マニュアルを作成することが大切です。実態に合わない安全マニュアルを作成したとしても、想定外の事故やケガの発生を予防できないだけでなく、迅速かつ適切な救急対応が妨げられることとなり、スポーツを楽しめる安全な環境を確保できていないことになります。
スポーツ現場の安全管理体制は所属する競技団体から発行されているガイドラインやマニュアルを踏まえて構築することをお勧めしますが、全ての団体がガイドラインを公開しているとは限りません。
中央競技団体が発行しているガイドラインやマニュアルを参考に、まずは、自分のチームの競技特性・活動内容・範囲に見合った最低限の内容から「こんな場合にはこうしよう」という手順を記載して共有するようにしていき、変化があればその都度、加筆修正し改訂していきましょう。
また、国際大会やプロチームなどと異なり、スポーツ少年団などでは予算も人のリソースにも限りがあります。このような制限がある中でどのように工夫し、安全を確保していくかを安全マニュアルの作成時に反映させる必要があります。
抜け漏れのない体制づくりに貢献
安全マニュアルを作成し、事前の体制づくりと事故後の対応を書面化することで内容に抜け漏れがないかを確認することができ、さらにスタッフ間での情報共有などの抜け漏れも最小限に抑えられます。
また、チーム内で実施される安全管理研修などを通して、保護者はチーム側がどれだけ安全に取り組んでいるかを把握でき、安心して子どもを預けられるようになります。
安全マニュアルの運用

安全マニュアルを作成した後は、1年に1度など定期的に確認することが大切です。指導者や保護者役員の交代などチームの体制が変わった場合などには、引き継ぎや見直しが必要です。
報道などにより、落雷事故などスポーツ現場で重大な事故が発生したことが明らかになった際には、改めて現在の自チームの安全マニュアルで迅速に対応できる体制が整っているかを安全管理担当者が中心となって検証し、見直しが必要な場合には改訂しましょう。
さらに、重大事故の調査委員会が公開する調査報告書や提言は重要です。調査委員会は弁護士や医師、専門家などの委員で構成されているため、より安全なスポーツ環境を実現するために何が求められているのかを確認することができます。
作成したことで終わったわけではなく、安全管理体制を常にアップデートする意識を持ちましょう。
